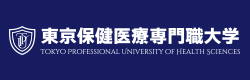お問合せ
- 西東京市社会福祉協議会
- 042-497-5061
お香典・相続財産・遺言による寄附のご案内
西東京市社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で生活ができるように、市民の皆様の理解と参加を得ながら”安心して暮らせるまち”を目指しており、その活動は会員会費や寄附金によって支えられています。
ご自身や故人の財産を地域の為に役立ててほしい、安心できる方法で信用できる地域の団体に寄附をしたい、という思いに応えるため、香典寄附、相続寄附、遺贈を承っております。
皆様のご厚意を心よりお待ちしております。